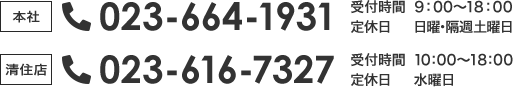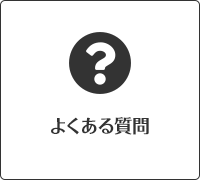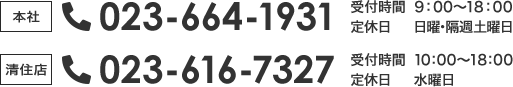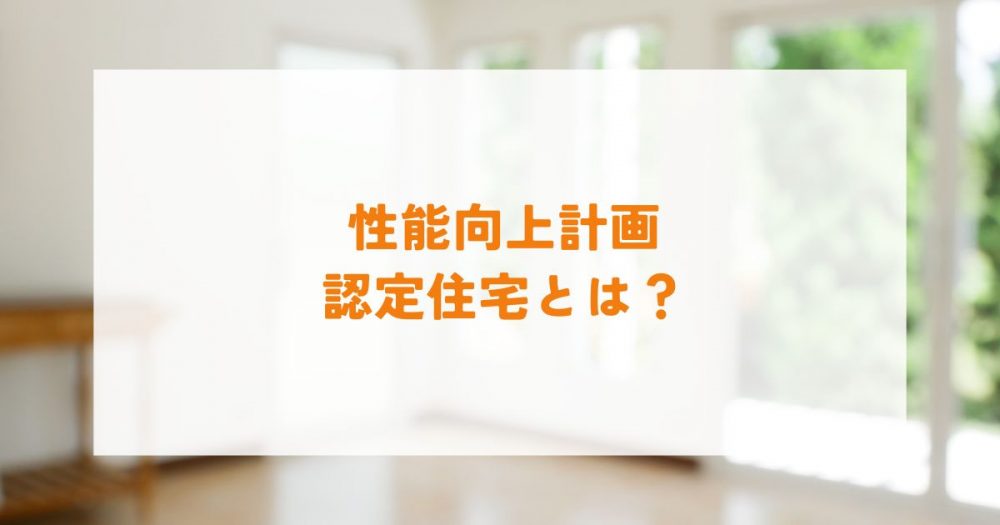
建築物のライフサイクルコスト削減や環境負荷軽減に貢献する様々な制度がありますが、その中でも「性能向上計画認定住宅」は、容積率特例という大きなメリットを持つ注目すべき制度です。
しかし、その制度概要や申請方法、他の省エネ制度との違いなどは、必ずしも広く知られているとは言えません。
本記事では、性能向上計画認定住宅のメリット・デメリット、そして取得方法について、皆様にとって役立つ情報を提供します。
性能向上計画認定住宅について、改めて理解を深めていきましょう。
制度概要と目的
性能向上計画認定住宅とは、建築物の省エネ性能が一定の基準を満たしている場合、国がその省エネ性能の高さを認定する制度です。
建築物省エネ法に基づき、新築、増築、改築、修繕、模様替えなど、省エネ性能向上を目的とした工事に対して認定が交付されます。
制度の目的は、建築物の省エネルギー化を促進し、地球温暖化対策やエネルギーセキュリティの強化に貢献することです。
容積率特例
性能向上計画認定住宅の主な特徴は、容積率特例です。
省エネ性能向上のための設備を設置する場合、その設備部分の床面積(上限10%)を容積率の計算から除外することができます。
これは、特に大規模な非住宅建築物において、燃料電池設備やコージェネレーションシステムなどの導入を促進する上で大きな影響力を持つでしょう。
容積率特例によって、建築可能な面積を増やすことができるため、設計の自由度を高め、より効率的な空間設計が可能になります。
太陽熱集熱設備、燃料電池設備、コージェネレーション設備、地域熱供給設備、蓄熱設備、蓄電池(再生可能エネルギー発電設備と連携した床置き型のみ)、全熱交換器などが、容積率特例の対象設備となります。
申請方法と必要書類
申請方法は、まず審査機関に技術的審査を依頼し、適合証の発行を受けます。
その後、適合証を添付した認定申請書を所轄行政庁に提出します。
最後に、所轄行政庁から認定証が交付されます。
具体的な手続きや必要書類は、所轄行政庁によって異なる場合があるため、事前に確認することが重要です。
一般的に必要な書類は以下です。
・認定申請書(所定の様式)
・設計内容説明書
・設計図書一式(平面図・立面図・断面図など)
・性能評価書の写し(住宅性能表示制度を活用する場合)
・省エネ性能等を示す計算書類(一次エネルギー消費量計算書など)
・建築確認申請書の写しまたは副本
・住戸面積・構造の確認資料
・その他自治体が定める書類(委任状、申請手数料納付書など)
申請に際しては、省エネルギー性能が建築物省エネ法に基づく誘導基準を満たしていること、建築物エネルギー消費性能向上計画の内容が基本方針に沿っていること、資金計画が適切であることなどが求められます。
また、複数の建築物を同時に申請する場合は、全てが誘導基準を満たしている必要があります。

省エネ効果と光熱費削減
性能向上計画認定を受けるためには、建築物の省エネ性能を向上させる必要があります。
これは、断熱性能の向上、高効率な設備機器の導入などを通じて実現されます。
結果として、光熱費の大幅な削減が期待できます。
例えば、ZEB(ゼロ・エネルギー・ビル)誘導基準を満たす工場では、一般的な省エネ建築物と比較して、年間40%以上の光熱費削減効果が見込まれます。
初期投資は高くなるものの、長期的な視点で見れば、光熱費削減によるコストメリットは非常に大きいです。
他の省エネ制度との比較
性能向上計画認定制度以外にも、低炭素建築物認定制度、ZEH(ゼロ・エネルギー・ハウス)など、様々な省エネ制度が存在します。
これらの制度は、それぞれ対象となる設備や基準、メリットが異なります。
低炭素建築物認定制度は、再生可能エネルギー利用設備の導入が必須で、都市におけるCO2削減措置も必要となるため、条件が厳しくなりますが、住宅ローン減税などの税制上の優遇措置を受けることができます。
一方、性能向上計画認定制度は、容積率特例が大きなメリットです。
どの制度が最も適しているかは、建物の規模、用途、予算、立地条件などによって異なります。
それぞれの制度の特徴を比較検討し、最適な制度を選択することが重要です。
資産価値向上と住宅ローン
省エネ性能の高い建物は、環境意識の高まりから、資産価値の向上に繋がります。
テナントビルであれば、光熱費削減効果と高い資産価値を訴求することで、賃料設定に有利に働くでしょう。
また、企業のESG投資への関心の高まりを受け、性能向上計画認定住宅を所有する企業は、高い評価を得る可能性があります。
さらに、フラット35Sなどの住宅ローンにおいても、省エネルギー性の基準を満たすことで、金利優遇などのメリットが得られる場合があります。

認定取得にかかる費用
性能向上計画認定を取得するには、申請費用、審査費用、省エネ設備導入費用など、様々なコストがかかります。
特に、省エネ設備の導入費用は、規模や種類によって大きく変動するため、事前に綿密なコスト試算が必要です。
容積率特例によるメリットが、これらの費用を上回るかどうかを慎重に検討する必要があります。
小規模な建築物では、認定取得にかかる労力と費用がメリットを上回ってしまう可能性もあるため注意が必要です。
申請手続きにおける注意点
申請手続きには、専門的な知識や手続きが求められるため、建築主や設計者は、専門機関の協力を得ることが重要です。
申請書類の不備や、基準への適合性の確認不足は、申請の遅延や却下につながる可能性があります。
また、容積率特例は、指定された省エネ設備を設置する部分の床面積にのみ適用されるため、単純に建築面積を10%増やせるわけではない点に注意が必要です。
認定取得までの期間
認定取得までの期間は、申請書類の審査や技術的審査などに時間を要するため、計画段階から十分な余裕を持ったスケジュールを立てる必要があります。
申請前に所轄行政庁に確認することで、必要な期間を把握し、スムーズな手続きを進めることができます。
性能向上計画認定住宅は、容積率特例という大きなメリットを持つ一方で、認定取得には費用と時間がかかります。
他の省エネ制度との比較検討、コスト試算、専門家への相談など、慎重な計画と準備が不可欠です。
しかし、光熱費削減効果や資産価値向上、環境への貢献といった長期的なメリットを考慮すれば、建築物にとって大きな付加価値となる制度と言えるでしょう。
◾️会員様限定プラン
①一般には公開していない会員限定の物件情報を閲覧可能♪
②物件情報ないのすべての投稿画像を閲覧できます♪
③希望条件登録機能でご希望の物件が販売されたらメールで通知!
◾️各種ご相談・お問い合わせはこちらから
ご売却/ご購入/お住み替え/リフォーム/リノベーション/その他お問い合わせ
◾️物件を探す/モデルルーム見学/資金について相談/その他
お電話でもお問い合わせ承ります☎️
リノベース 清住ショールーム TEL :023-616-7327
Youtube
最新のお役立ち情報やリフォーム・リノベーションの施工事例など公開中
最新のお役立ち情報やリフォーム・リノベーションの施工事例など公開中
最新のお役立ち情報やリフォーム。リノベーションの施工事例など公開中